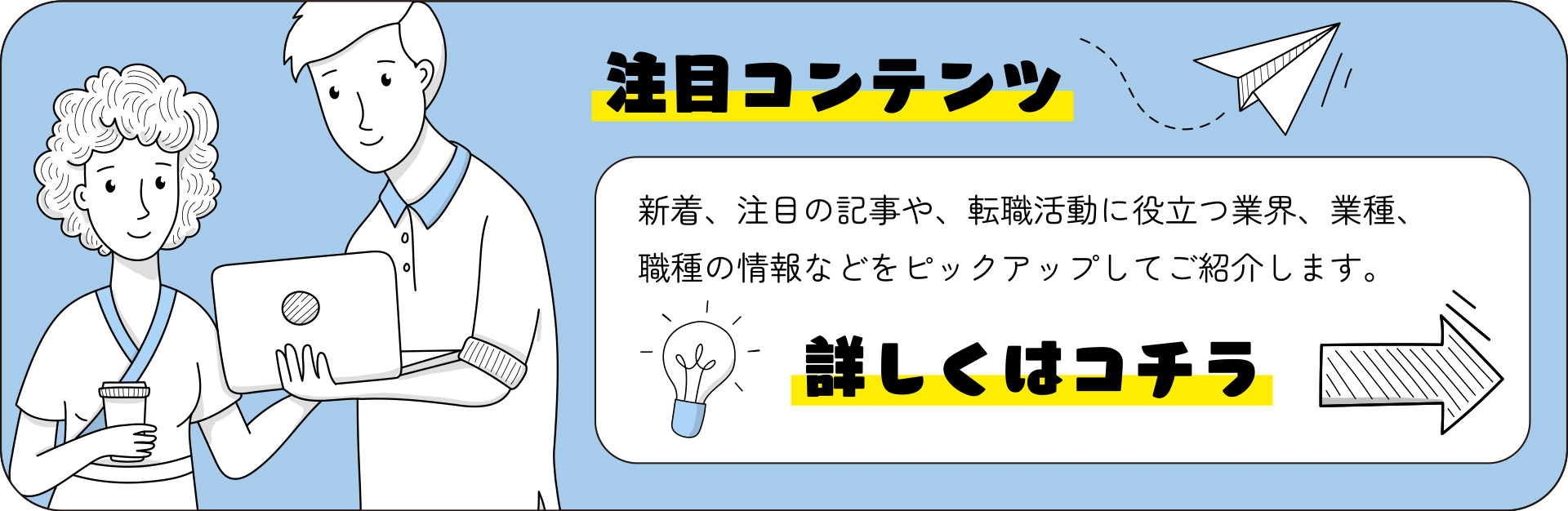工場で最悪な人間関係は、挨拶もすらない状況であり、仕事に対するやりがいを感じることができません。 周…
【給料より「安定」を選ぶ人が増えている?】2025年のリアルな職場選び
給料よりも「安定」を選ぶ人が増えているのではないか、と感じる方も多いのではないでしょうか。
物価高や増税で将来への不安が高まっているため、安定した働き方に関心が高まっています。
本記事は、給料よりも「安定」を選ぶ人が増えている理由から2025年リアルな職場選びまでを詳しく解説します。
また2025年安定して働ける職種を紹介していますので、参考にしてください。
※工場求人のお仕事をお探しの方は、しごとアルテがオススメ。
しごとアルテは、【時給2100円、年収例555万円、寮費タダ】など、全国1000件以上の求人を取り扱っております。
目次
給料よりも「安定」を選ぶ人が増えている理由
給料よりも「安定」を選ぶ人が増えている理由は以下の通りです。
- 物価高や増税で将来への不安が高まっている
- 給料が高くても長く続けなければ意味がない
- キャリアよりも生活を重視する人が増えている給料よりも安定を選ぶ人が増えているのかを知りたい方は、上記の内容を見ておきましょう。
それぞれ解説します。
物価高や増税で将来への不安が高まっている
近年、給料の高さよりも安定した雇用を重視する人が増えています。
物価高や増税によって生活費の負担が増し、将来の家計見通しが立てにくくなっているからです。
収入が一時的に高くても、景気や会社の業績によって雇用が不安定になるリスクを避けたいと考えている人が増えています。
食費や光熱費の値上げが続き、生活に必要な支出は数年前より明らかに増加傾向です。
また社会保険料や消費税などの負担も上昇しています。
生活費や財負担の増加により家計の不安が広がるなか、収入額以上に雇用の安定が求められています。
給料が高くても長く続けなければ意味がない
給料が高くても長く続けられなければ意味がないため、安定を選ぶ人が増えています。
短期間で収入が途切れれば、生活設計が崩れやすくなるからです。
特に物価高や増税が続く中では、将来の収入や雇用が予測しにくくなり、不安定な職場よりも長く続けられる環境を選ぶ人が多くなっています。
たとえば、公務員や医療、インフラなどの職種は、給与が平均的に安定しており、将来設計がしやすいことから人気があります。
給料の高さだけでは生活の安心感は得られません。
自分に合った仕事であれば、長期的に安心して働き続けられます。
キャリアよりも生活を重視する人が増えている
給料よりも安定を選ぶ人が増えているのは、キャリアよりも生活を重視する人が多いためです。
昇進や高収入を目指すよりも、確実に収入が入り続ける環境や、ワークライフバランスが保てる職場を優先する人が増えています。
たとえば、残業や休日出勤が多い仕事に転職すれば収入は上がりますが、旅行や推し活などの趣味に割ける時間が減ります。
しかし、給料はほどほどでも残業が少なく、定時に帰れて趣味や家族との時間を確保できる職場のほうが人気です。
お金よりも、自分らしく暮らせる時間や趣味を楽しむ余裕を守ることを、多くの現代人が求めています。
安定している職場の特徴
安定している職場の特徴は以下の通りです。
- 景気に左右されにくい業界
- 働き方が柔軟で無理なく続けられる
- 教育・研修体制が整っている
安定している職場で働きたい方は、上記のような特徴を押さえておきましょう。
一つひとつ解説します。
景気に左右されにくい業界
安定している職場の特徴は、景気に左右されにくい業界であることです。
景気の変動が大きい業界では、業績悪化による人員削減や給与カットのリスクがあるからです。
一方で、景気の影響を受けにくい業界は需要が安定しており、長期的に雇用を維持しやすくなります。
たとえば、医療や介護、インフラ、教育、公務員などは、多くの人の生活に直結しているため、不況時でも需要が減りにくいです。
新型コロナの影響で観光や飲食が打撃を受けた一方、医療や物流は人手不足が続き、雇用が安定していました。
安定した職場を見極めるには、業務内容や給与だけでなく、その業界が景気変動にどれだけ左右されるかを確認することが大切です。
働き方が柔軟で無理なく続けられる
どれほど給与や雇用が安定していても、長時間労働や休日が取れない環境では、心身に負担がかかり、長く続けられません。
柔軟な働き方ができる職場は、ライフスタイルの変化や体調の変化にも対応しやすく、結果的に離職率が低くなります。
たとえば、フレックスタイム制度やリモートワークが導入されている企業は、子育てや介護をしながらでも働き続けやすいです。
急な体調不良や家庭事情にも柔軟に対応できるため、従業員の満足度も高く、職場の定着率が上がります。
安定した職場とは、雇用や給与面だけでなく、働く人が無理なく長く続けられる柔軟な環境です。
教育・研修体制が整っている
教育や研修が充実している職場は、従業員のスキル向上や業務のマニュアル化が進みます。
そのため、ミスやトラブルが減り、長期的に安定した運営ができます。
また働く側にとっても成長の機会が確保されるため、安心して働き続けやすいです。
たとえば、新入社員研修や定期的なスキルアップ講習がある企業は、経験がなくても業務を覚えやすいです。
教育・研修体制が整っている職場は、従業員と企業の双方にとって安定をもたらします。
2025年のリアルに重視される職場選び
2025年のリアルに重視される職場選びは以下の通りです。
- 安定収入を得られる職場か
- 残業時間が具体的に提示されているか
- 離職率が低いかどうか
- 福利厚生が充実しているか
- 職場の雰囲気や人間関係が良好か
自分に合った職場を見つけたい方は、上記の選び方を把握しておきましょう。
詳しく解説します。
安定収入を得られる職場か
物価上昇や社会保険料の負担増など、生活コストが高騰しているため、収入が不安だと将来設計が難しくなります。
また副業や投資など複数の収入源を持つ人が増えている一方で、本業の収入の安定性は生活の基盤として欠かせません。
不安定な収入だと、住宅ローンや教育など長期的な出費の計画が立てにくく、生活に大きな不安を抱えることになります。
将来のライフプランを守るためには、変動が少なく、継続して生活費をまかなえる職場を選ぶことが大切です。
残業時間が具体的に提示されているか
職場選びでは、求人票に残業時間が具体的に提示されているかどうかが重要な判断材料になります。
求人票に「残業あり」「月20時間程度」といった曖昧な記載しかない場合、実際にはそれ以上の長時間労働になるケースも少なくありません。
具体的な数字や繁忙期・閑散期の差が明示されていれば、入社後のギャップを避けやすくなります。
給与や福利厚生だけでなく、残業時間の透明性も職場選びの基準といえます。
離職率が低いかどうか
離職率が低い職場は、労働環境や人間関係、待遇などが安定している可能性が高いです。
逆に離職率が高い企業は、長時間労働や低待遇、組織内のトラブルなど何らかの課題を抱えていることが多く、入社後のミスマッチにつながります。
また近年は転職市場が活発ですが、短期間で転職を繰り返すことはキャリア形成にも不利になります。
そのため、長く働ける環境を事前に見極めることが大切です。
企業の採用サイトや、転職サイト、口コミサイトを活用して、情報収集するようにしましょう。
福利厚生が充実しているか
物価や医療費の上昇、老後資金への不安などから、給与以外のサポート制度が生活の安定につながります。
福利厚生が整っていれば、出費を抑えつつ安心して働けるため、長期的に勤務を続けやすいです。
たとえば、住宅手当や育児休暇後の短時間勤務制度、在宅勤務用の通信費補助などがあれば、生活が充実します。
長く安心して働くためには、給与だけで判断せず、福利厚生の種類や条件を事前に確認することが欠かせません。
複数の企業を比較し、自分に合った条件がある職場を選ぶことが重要です。
職場の雰囲気や人間関係が良好か
職場選びでは、給与と待遇と同じくらい、職場の雰囲気や人間関係の良好さが重要な判断基準になります。
職場の人間関係が悪いと、日々の業務がストレスになり、長期的に働き続けることが難しくなるからです。
しかし、良好な雰囲気であれば、困ったときに相談しやすく、モチベーションの維持につながります。
たとえば、同じ業務量でも上司や同僚が進捗を気にかけてくれたり、失敗したときにフォローしてくれたりする職場では、安心してチャレンジできます。
面接時に質問したり、職場見学で雰囲気を確認したりすることで、自分に合った仕事かどうか判断できるでしょう。
***
働きやすさのヒミツはコチラから!↓↓
職場選びでありがちな失敗パターン
職場選びでありがちな失敗パターンは以下の通りです。
- 「なんとなく」で決めて後悔する
- 自分の優先順位を明確にしないまま応募してしまう
- 求人票だけを信じて現場を見ていない
自分に合った職場を選びたい方は、あらかじめありがちな失敗パターンを知っておくことで回避できます。
それぞれ解説します。
「なんとなく」で決めて後悔する
職場選びを「なんとなく」で決めると、高確率で入社後に後悔します。
求人票や面接での第一印象だけで判断すると、仕事内容や人間関係、働き方の実態などの重要情報を見落としがちです。
条件を深く確認しないまま入社すると、想定外の残業、合わない社風、昇給制度の不透明さなどに直面し、早期退職につながります。
たとえば、雰囲気が良さそうな印象だけで入社すると、実際は上下関係が厳しく、意見を言いにくい場合があります。
職場選びは、感覚や一部の条件だけで判断せず、仕事内容や給与、福利厚生、職場の雰囲気など複数の情報源を確認して総合的に判断することが大切です。
自分の優先順位を明確にしないまま応募してしまう
職場選びで自分の優先順位を決めずに応募すると、入社後に条件や環境が合わず、早期退職につながりやすくなります
給与や勤務地、残業時間、やりがいなど、職場に求める条件は人によって異なるからです。
優先順位を決めておかないと、求人を見たときに目先の魅力だけで引き寄せられ、本来重視すべき条件を満たさない職場を選ぶ危険性があります。
求人探しのまえに自分が大切にしたい条件を3つ程度に絞り、その順番を明確にしておくことが欠かせません。
優先順位がはっきりしておけば、魅力的に見える条件があっても冷静に比較でき、長期的に働ける職場を選びやすくなります。
求人票だけを信じて現場を見ていない
求人票の情報だけを信じて応募・入社すると、実際の職場環境とのギャップで後悔する可能性が高くなります。
求人票には基本的な条件や会社の魅力が書かれていますが、実際の雰囲気や人間関係、仕事の進め方まではわかりません。
また求人票の表現は応募者に魅力的に見えるよう工夫されているため、現場の実態との差がある場合もあります。
現場を確認しないまま入社すると「思っていたいのと違う」「想定外の業務が多い
などのギャップが生じやすいです。
面接時に現場を確認する、社員と直接話す、口コミサイトで情報を補足するなどで確認することで、後悔しない職場選びにつながります。
2025年安定して働けるおすすめの職種5選
2025年安定して働けるおすすめの職種5選は以下の通りです。
- 製造業
- インフラ系
- 公務員
- 医療・介護・福祉系
- 物流・倉庫
安定して働きたいけど、どのような職種がいいかわからない方は、上記のおすすめを見ておきましょう。
詳しく解説します。
製造業
製造業は自動車、半導体、食品、医療機器など幅広い分野があり、景気や社会情勢の変化に強い領域も多いです。
近年は生産ラインの自動化や省人化による効率化が進み、長期的な雇用需要が見込まれます。
またスキルや資格が蓄積しやすく、経験が転職や昇給につながるため、キャリアの安定性も高い業界です。
研修や教育体制が整っている企業も多く、未経験者でも挑戦しやすいです。
製造業は業種や企業によって仕事内容や職場環境がことなるため、応募前に確認すると、長く安心して働ける職場を見つけやすくなります。
インフラ系
安定して働ける職種のひとつは、電気・ガス・水道などのインフラ系です。
インフラは生活や経済活動の基盤であり、景気や流行に左右されにくい特徴があります。
また水道や電気の多くは、法律や自治体との契約に基づいて運営されているため、雇用や収益の安定性が高いです。
長期的な雇用と安定収入を求めるなら、社会に不可欠なサービスを支えるインフラ系がおすすめです。
資格手当や安全手当などの福利厚生が充実し、安定した給与体系が整っています。
公務員
公務員は国や自治体の組織に属し、景気変動や企業業績に左右されにくい安定した雇用が特徴です。
給与や昇給制度、退職金制度が明確に定められており、長期的な生活設計を立てやすい点も魅力です。
また福祉や教育、防災などの幅広い分野があり、社会貢献度の高い業務に携われます。
たとえば、市役所職員や県庁職員は、地域の福祉サービスやまちづくりを支える役割を担います。
長期的な雇用と安定収入を求めるなら、公務員は魅力的な選択肢です。
医療・介護・福祉系
少子高齢化が進む日本では、医療や介護、福祉の需要が今後も増え続けます。
景気変動や企業業績の影響を受けにくく、社会に不可欠な分野であるため、雇用が途切れにくいのが特徴です。
また資格や経験が直接的にキャリアの安定に繋がりやすく、一度スキルを身につければどこでも働き口を見つけやすくなります。
医療や介護、福祉系は、資格手当や夜勤手当、住宅手当など給与以外の待遇が充実している場合も多いです。
応募前には、必要資格や研修制度、勤務形態を確認して、自分のライフスタイルに合った職場を選ぶようにしましょう。
物流・倉庫
EC市場の拡大やさまざまな配送ニーズの増加により、物流・倉庫業界は安定した需要があります。
日用品や食品、医薬品などの生活必需品の輸送は景気変動の影響を受けにくいです、
また自動化やAIによる効率化が進んでも、人手による現場作業や管理業務は引き続き必要とされるため、雇用は途切れにくい業界です。
フォークリフト免許や危険物取扱などの資格を取得すれば、キャリアアップや給与増加のチャンスがあります。
近年は働き方改革の一環として、シフトの柔軟化や時間短縮制度を導入する倉庫も増えています。
まとめ
2025年は物価高の影響で、給料の高さよりも長く安定して働ける職場を重視する人が増えています。
安定している職場は景気に左右されにくく、働きやすい環境や研修制度が整っている点が特徴です。
職場選びでは、収入の安定性や福利厚生、人間関係といった要素を確認し、自分に合った環境を見極めることが大切です。
***